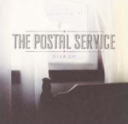 |
Give Up / The Postal Service |
|||||
| こぢんまりとしたペット・ショップ・ボーイズ' 的サウンドのThe Postal Service。Death
Cab for CutieのBenjamin Gibbard、DntelのJimmy Tamborelloが中心となり、互いのアイデアやサウンドを、ポスタル・サービス(郵便)を介して交換したことから、このバンド名が名づけられたという。Jimmy
Tamborelloがエレクトロニク・サウンドを担当、クリエイトしたものをBenjamin
Gibbardに郵送し、そのパートにBenjamin Gibbardがギター、ボーカル、歌詞を付けていった過程、それがアルバム『Give
Up』となった。きっとこの2人、定期的に「ポストを覗く」という行為を、健全に楽しんだに違いない…。 初めてThe Postal Serviceのサウンドに触れたとき、ヒューマンな温もりと、優しい印象を受け、心地よい時間の流れを感じた。まるで、綿菓子で作られた乗り物で、ふわり空を漂っているような感覚。そして、キャッチーでクリアなメロディに、自然と、身体を揺らし、微笑んでしまう自分がいるのだ。決してドラマティックではないのだが、「等身大」で表現することが、何だかとても輝いて見える作品。確かにシンセサイザーが前面にあるものの、無機質なサウンドに陥ることなく、エモーションの極みを追求しているのは涙もの!その理由は、Benjamin Gibbardの声にある。ペット・ショップ・ボーイズ、ニール・テナントの「声の癒し」(ニールの声は、誰が聞いても心を癒される、特別な声の持ち主と言われている)を、少なからずBenjamin Gibbardの声にも感じるのだ。特に#3 『Sleeping In』 は、ピコピコ・サウンドに、Benjamin Gibbardのポップセンスが絶妙にマッチした珠玉作!「don't wake me I plan on sleeping in」と、メロウな声で、繰り返し歌われたら、この上なく幸福な気分になり、泣けてくる…。この4分21秒は、心の洗浄タイムだ。 『Give Up』は、サブポップからリリースされた。このレーベルのシャープな音楽視点は、個人的に、新鮮な驚きを感ぜずにはいられない。特に、アーティストのサイドプロジェクトには、多大な理解を示していて、素晴らしい作品がサブポップからリリースされている。The Postal Serviceしかり、Ugly Casanovaしかり。(最近、メディアを賑わせているHot Hot Heatも、サブポップのバンドということを挙げておこう)The Postal Service は、7/8にシングル『The District Sleeps Alone Tonight』をリリース。ザ・フレーミング・リップスの『Suddenly Everything Has Changed』をカバーしているのにも注目だ。 ところで、「サブポップ」が「ボブサップ」に見えてしまう人って、結構いるのだろうか?この目の錯覚って、かなり笑えると思いません? http://www.subpop.com |
||||||
| Utayo Furukuni | ||||||
 |
Lowedges / Richard Hawley |
|||||
| 前作 『Late Night Final』 はタイトル通り底しれない夜の深みにはまりこんでもがきながらも、その暗さを受け入れたような男の姿が描かれていた。自分が一人であることをかみしめるような、孤独と酩酊。 今作では、その暗い夜があけ、明るい光がさしこんできたような清澄な空気がある。静かな決意を語る一曲目 『Run For Me』 から、帰る道を見失い、トホホな状況の中歌われる 『The Motorcycle Song』はまるで「闘いすんで日が暮れて・・・」のようだ。黄昏から夜に向かう時間の中で見つめる自分自身・・・。ここにはそんな男の一日が凝縮されている。多用されるハワイアン・ラップ・スチールはもっかのお気に入りのようだ。通常はシンセで処理されてしまう音をていねいにギターで表現している。微妙なゆれと息遣いが感じられるのだ。 マイ・ベストは 『The Only Road』。リピートで20回聴いてもあきない。静かに流れるメロディに、押さえたヴォーカル、寄り添うようなバック・ヴォーカル。淡々としたベースに、一瞬ルー・リードの『ワイルドサイドを歩け』を思い出した。、しだいに重なっていく多様なギター音。静寂の中の広がり。このアルバムと同時にニール・ヤングの「ハーヴェスト」「ハーヴェスト・ムーン」をCDで買い直したのだが、共通するものがあって驚いた。シンクロしている。静かで、せつなく、深い。 アダルト・ロックとか、リリカル・ロックとか形容されている最近の彼だが、無器用な男どもが集まって懸命に愛や家族や人生を語っている・・・そんなところが、これまた無器用な男たちの共感を得ているのだろうなと思った。心配された指の骨の移植後の経過も順調のようだし、やはりリチャードにはガンガン弾きまくってほしい! 歌詞はリチャードのHPで http://www.richardhawley.co.uk/Discography.html |
||||||
| Y. ISE | ||||||
 |
Source Tags & Codes / ...and You Will Know Us by The Trail of Dead |
|||||
| トレイル・オブ・デッドのニュー・アルバム 『Source Tags & Codes』 が遂にリリースされた。前作
『Madonna』 より、約2年半という月日を経て、彼たちのベールが剥がされ、確かな形として表出した作品である。その間、イギリスで先行ブレイクを果たし、メジャー・レーベル、インタースコープとの契約を結んだ。サマーソニック2001で初めて日本の地を踏み、5月には『Source
Tags & Codes』の日本盤がリリースされる運びとなった。 巷のレコード店や、日本のミュージック・プレスからは「ニルヴァーナ以来の衝撃」「オルタナティヴの申し子」とまで書かれ(そういった考えとは全く違う次元に、私はいるのだが…)、いまや彼たちの存在は、誰もが認めるところとなった。個人的に彼たちのカリスマ性を確信していたとは言え、ここまでしてやってくれると、にやりとしてしまう。「嵐はすぐそこまで来ているぞ!」これは、彼たちに魅了され、音楽に圧倒され、会う人会う人に、トレイル・オブ・デッドの存在誇示をプッシュした、私の口癖だった。人間というのは不思議なもので、本当に自分が好きなものを、直感でわかってしまう動物だ。私にとってトレイル・オブ・デッドは、その直感が、何の疑いもなく瞬時に働いたバンドである。そう、エキサイティングな出来事は常に突然やって来るのだ。 セカンド・アルバム 『Madonna』 で、彼たちが体現したダダイズムへの返答に、私はすっかり打ちのめされ、ジャンクで歪んだノイズ・サウンドに、自分を無防備にさらけ出した。ゆえにこの時点で、ニュー・アルバムの話題になる度、その期待は宇宙船のごとく大きく、私の中で膨らんでいた。だが、セカンド・アルバムに対する、自分の固定概念があるせいか、『Source Tags & Codes』 を最初聴いた時、ファーストとセカンドで表現された、ラフさ、疾走感が押さえられた気がした。正直「これがトレイルなのか?」と思ったほど、サウンドがクリアになっていた。戸惑いというより、驚きという言葉が適切だろう。 以前、コンラッドはこう言った。「素晴らしいアルバムを作ることは重要なんだ。グレイトなライヴ・バンドでも、ひどいレコードを作っている場合があるしね。俺たち、ステージではかなりハードだけど、だからってスタジオでは、ライヴ・サウンドをクリエイトしようとは思わない。スタジオでは楽器を使ういい機会なんだ。ライヴとは違ったことをするという…」その通りだ。ライヴのインパクトが強烈だからと言って、アルバムが色褪せてしまうなんてナンセンス。トレイルはアルバムごとに、全く違ったアティチュードで、音楽をアートとして表現しようとしている。また今回は、ギリギリの危うさ、抑圧の中に存在する狂気が更に増している。 私が「これがトレイルか?」と思ったなら、それは彼たちのサウンドが、新しいアスペクトを持ったということになり、またまた、彼たちにサプライズしてしまったわけだ。改めてCDプレイヤーをオンにした。すると、彼たちのサウンドは、有無を言わせず、真っ直ぐ私の心臓を突き抜けてきた。 『It Was There That I saw You』 『Another Morning Stoner』 で、トレイル・オブ・デッドが持つサウンドの魅力で、ハイテンションになった。『Baudelaire』 から 『Homage』 に入る間奏では、「セカンドにも似たような音作りがあったなぁ」と、思わずにんまり。そして『How Near How Far』。私は今アルバムの中で、この曲をこよなく愛している。センチメンタルなメロディーに、ドラミングが強烈にかぶさり、私は思わず、この曲を聴きながら、その場にうずくまってしまった。そう、トレイルの素晴らしさは、曲そのものに、確かなメロディーがあるのだ。ただ単に、疾走感のあるノイズバンドではないのだ。『Monsoon』 でのジム・モリソンばりのヴォーカル、ヴードゥーなループ・サウンドに身体が熱くなる。 アルバムを締めくくるラスト・ソング 『Source Tags & Codes』 の、軽快なメロディーに、トレイル・オブ・デッドの多様性を感じた。昨年のサマーソニックでは、すでに 『Homage』 と 『Relative Ways』 をプレイしていた。ある意味、次のサウンドの予測は、ここからも立ったわけだが、いやはや、これはただの前哨戦であったのだ。『Source Tags & Codes』 は、アメリカのカレッジ・チャートでも1位を獲得。行く先々のライヴは、チケットが必ずソールドアウト。この快進撃を、自分たちのペースで、いつまでも続けて欲しい。 |
||||||
| 古國 宴代 Utayo Furukuni | ||||||
 |
○ / AC Acoustics |
|||||
| 2000年発表の Understanding Music から2年、AC Acoustics の新作『○』が届いた。 うーっ、しかしこのタイトルどう読めばいいんだ?「マル」か?「円」か「サークル」か?意地悪なやつらである。謎をかけている。ミステリー・サークルである。屈折しているのだ。それにカヴァーの馬人。その眼の凶々しさ。『エクウス』(EQUUS、ラテン語で馬)という舞台劇がちらと浮かんだ。 前作 Understanding Music は力強いアルバムだった。シンフォニックな厚みのあるアレンジでぐいぐい押してくるし、旋律もくっきりしていて、ブルージーなRidley RiderなどはAC にはめずらしい“歌える”曲だった。今作ではシンセがやや後退した分、よりアレンジに溶けこんだものになっている。 私は、彼らが作り出す音のタペストリーとでもいうべきもの、あるいは個々の音のモザイクといってもいいが、怒涛のギター音とベース、ドラムスの配置に微妙にヴォーカルがからまるコンポジションの多様性にひかれている。だから、ここ、というときにカーンとひびくドラムの一撃、あるいはベースの一音が組みこまれた曲に非常に執着してしまう。そういう意味で残念ながら今回はまだ「これ」という曲を見出せないでいる。しかしACはするめバンドなので咀嚼し続ける必要があるのだ。 ACはとてもやっかいなバンドだ。売り出すためのキャッチーなシングル、だれもが口にできるメロディや歌詞、というものとはあまり縁がない。ACが批評家からは毎作高い評価を受けながら、ポピュラーな人気を獲得できないでいるのはそのせいだ。(本人たちはヘとも思わないだろうが)つまりカラオケで歌えない、カラオケにはならない曲ばかりなのだ。人がヒット曲に期待するワクワク・ドキドキ感、浮遊感を、ACはさらりとかわしてしまう。ものすごく熱く見えるのに、さわるとひやりとしている。そこで尻込みしてしまう人が実に多いのだ。もう少し近づいてくれたら、そのひやりとした膜の下に熱いものが沸騰しているのがわかるのに。それを端的に示してくれるのがライブなのだが、クソ!日本にいては手も足も出ない!ライブ・アルバム出してくれないかな? このレヴューを書いた直後、ACのギタリスト、マーク・レインからメイルが届いた。「ACは解散。メンバーはそれぞれの道を」 |
||||||
| by Ise | ||||||
 1.Fight Test 2.One More robot/Sympathy3000-21 3.Yoshimi Battles The Pink Robots pt.1 4.yoshimi battles The Pink Robots pt.2 5.In The Morning Of The Magicians 6.Ego Tripping At The Gates Of Hell 7.Are You A Hypnotist?? 8.It's Summertime 9.Do You Realize?? 10.All We Have Is Now 11.Approaching Pavonis Mons By Balloon (Utopia Planitia) |
Yoshimi Battles The Pink Robots / The Flaming Lips |
|||||
| イギリス、アメリカでは勿論のこと、日本でも大絶賛を浴びている『Yoshimi Battles
The Pink Robots』。私はニュー・アルバムを聴いた瞬間、『The Soft Bulletin』同様、ここ数十年のクラシック・アルバムになり得る傑作だと感じた。それぞれの曲のカラーが、それぞれの個性で鮮烈に際立っており、エモーショナルなマジカル・サウンドは、時に激しく、時に柔らかく、我々の感情をかき立て、更なるリップス・ワールドを表現している。聴いた瞬間、光速で、別世界へと旅立ってしまった。 そして、やはりリップスの奏でるメロディーの素晴らしさに、思わずしくしく泣いちまった私…。まず、『Fight Test』の軽快サウンドと、ウェインのルースでリラックスしたボーカル・スタイルに、一気にニュー・アルバムの期待感が膨らんだ。そして、次に流れる『One More Robot/Sympathy 3000-21』で、完全にノックアウト!リップスの意図するニュー・サウンドを、ダイレクトに、リアルに体感、静かなる興奮が身体中に纏わりついて離れない。この曲はドラム&ベースが基調となっているが、バラード調の美しいメロディーが心に響く。そこへ『Yoshimi Battles the Pink Robots pt.1』のような柔らかタッチのサウンドが届けられ、『Yoshimi Battles the Pink Robots pt.2』では、ヨシミの“華麗なる叫び”が待ち受けている…。この流れは、“ロボットと人間”というカートゥン・イメージを、彼たちの遊び心とイマジネーションで、パーフェクトに表現していると思った。バックで聴こえるヨシミの日本語や絶叫は、これまた不思議な呪文のように、リスナーの心を透き通った膜で包み込んでくれるはずだ。そう…まるでオブラートのように。 さて、『In the Morning of the Magicians』からは、これまでのサウンドとは全く異なり、リップスは私たちを、トリップ感のある、幻想的な世界へと招待してくれる。そこでは、ゆったりと、力強く、私たちの時間が回り続けていくかのようだ。ニュー・アルバムにおいて、ウェインが最もボーカルに集中したと言う『Ego Tripping At the Gates of Hell』は、とても浮遊感のある美しいメロディー。スティーヴン曰く「これまでウェインが歌った曲の中で、最高のボーカル」と評していた。死生観をフィロソフィカルに謳い上げた『It's Summertime』、そして『Do You Realize?』で、リップスはこう歌っている。「わかるかい?君の顔はとてもきれいだ。わかるかい?僕たちは宇宙を漂っている。わかるかい?幸せで泣けてしまうんだ。わかるかい?君が知る全ての人間は、いつか死ぬんだよ…」人々は、このあまりにエモーショナルで、センチメンタルなメロディーと歌詞に、何を感じるのだろう…。誰もが分かりきったことだとしても、誰がそのことを歌っただろう…。その優しさが痛いほど心にフィルターされて、泣けてくる。それは悲しみよりも、歌詞にあるように、生きていることを実感しながら「幸せで泣けてしまう」そのものなのだ。真に、リップスを語るに相応しい名曲である…。ラジオからこの曲が流れた瞬間、耳を傾け、感情の爆発を体験する人がどれだけいるだろう。それを想像するだけで、エモーショナルになってしまう自分がいる。今夏イギリスで、この曲はきっとセンセーションを巻き起こす。BBC RADIO 1の大御所DJ、ジョン・ピール御大も、XFMの名物DJ、ジョン・ケネディーも、目頭を熱くして、ヘビー・ローテーションするだろうこれは名曲だ。 フューチャリスティックな『Approaching Pavonis Mons By Balloon (Utopia Planitia)』で閉幕するこのアルバム。未来はいつまでも続く…、未来は自分たちの中にある…、そのようなエネルギーを体感できるインスツルメンタルだ。 今アルバムでは、スティーヴンがドラムをプレイしていない。ドラム・マシーンでのレコーディングだった模様。これはウェインのアイデアらしいが、最初、あまりに突飛なこのアイデアに、バンド周辺はおののいたそうだ。(笑)しかし、ウェインのインタビューにもあるように、「スティーヴンだったら、新しい何かが、必ず出来るはずだ」という、彼の才能に確信を持った結論である。ゆえに、真のクリエーターは、何をやっても結果を残すのだ。脱帽…。 今回のプロデューサーも、我らがデイヴ・フリドマン!とフレーミング・リップス。以前、ウェインとインタビューをした時に、「デイヴのスタジオは器材の洞窟みたいなんだ」と言っていた。なるほど、ここには、器材の洞窟のみならず、人間の思考洞窟も存在するのだと思った。器材だけでは、これほどまでのアイデアが、アルバムに反映されるわけがない!ハプニングの楽しみを誰よりも知っているデイヴとリップス、本当に最強なコンビネーションだ。「ミレニアムって一体何だったの?」と首を傾げたくらい、リップスのニュー・アルバムによって、初めて自分は、新時代の扉を叩いたのだと実感した。ここ数十年のクラッシック・アルバムが、今ここに完成!希望をありがとう。 |
||||||
| 古國 宴代 Utayo Furukuni | ||||||
| Update | Feedback | Contact |